発達障害=できない ではなく「違うやり方」が必要なだけ
- Colorful Kids

- 2025年8月15日
- 読了時間: 3分
「どうしてこんな簡単なことができないの?」「何度言っても覚えられない…」
そんなふうに感じたことがある方、もしかしたらいませんか?
でも実は、“できない”のではなく、「そのやり方が合っていないだけ」かもしれません。
発達障害の特性を持つ子どもたちや大人たちは、「やり方を少し変える」ことでグンと力を発揮できることが多くあります。
今回は、“できない=能力が低い”ではないという視点で、「違うアプローチで可能性が広がる」ことを紹介していきます。
もくじ
できないのではなく、伝わっていないだけかも?
発達障害のある人は、情報の受け取り方・整理の仕方・表現の仕方が“ちょっと違う”ことがあります。
例えば、
・口頭での説明が苦手 → 図形や写真にするとすぐ理解できる
・マルチタスクが難しい → 1つずつ順番にやればしっかりこなせる
・時間の感覚が掴みにくい → タイマーやビジュアルスケジュールで管理できる
「何でできないの?」ではなく、「どう伝えたらできるかな?」という視点がとても大切です。

本人のやる気や努力不足ではない
「努力すればできるはず」「やる気がないだけじゃない?」と思われがちですが、発達障害の特性により、脳の使い方や感じ方が根本的に異なることがあります。
これは本人のせいではなく、“努力ではどうにもならない壁”があることも多いのです。
でもその壁は、やり方を変えることで乗り越えられることもあります。
「違うやり方」を見つけるヒント
では、どうやって「その子に合ったやり方」を見つけていけばいいのでしょうか?
以下のようなポイントがヒントになります。
・得意な感覚を探す:視覚が得意、音声が入りやすい、体を動かすことで覚えやすいなど
・工程を細かく分ける:1つの作業をステップごとに分解
・本人に確認する:どう説明されたらわかりやすい?どうしてやりにくい?など対話する
周囲が「柔軟に変えてみる」ことで、驚くほどスムーズに進むケースも多いです。

やり方が違えば、可能性が開く
例えば、ある子は「文章の読み取りが苦手」だったのに、図で見せると内容を正確に理解し、説明までできるようになった…というケースもあります。
また、大人になってから「自分は聴覚情報に弱い」と気付いた方が、会議でボイスレコーダーを使い、後から文字に起こして確認することで仕事が円滑に進むようになった例も。
やり方を変えるだけで、「できる」が引き出せる。
これは発達障害のある方にとって、とても希望の持てる視点です。
まとめ
発達障害=できない、という考え方は、もう過去のもの。
本当は、やり方が合っていないだけで、できる力を持っている人がたくさんいます。
だからこそ、こちらが伝え方や環境を「違うやり方」に変えることがとても重要です。
それは特別なサポートというよりも、“ちょっとした工夫で人生が変わる”アプローチ。
「この子には何が合ってるかな?」
そんな問いかけをしながら、一緒に可能性を引き出していけるようにしていきましょう。

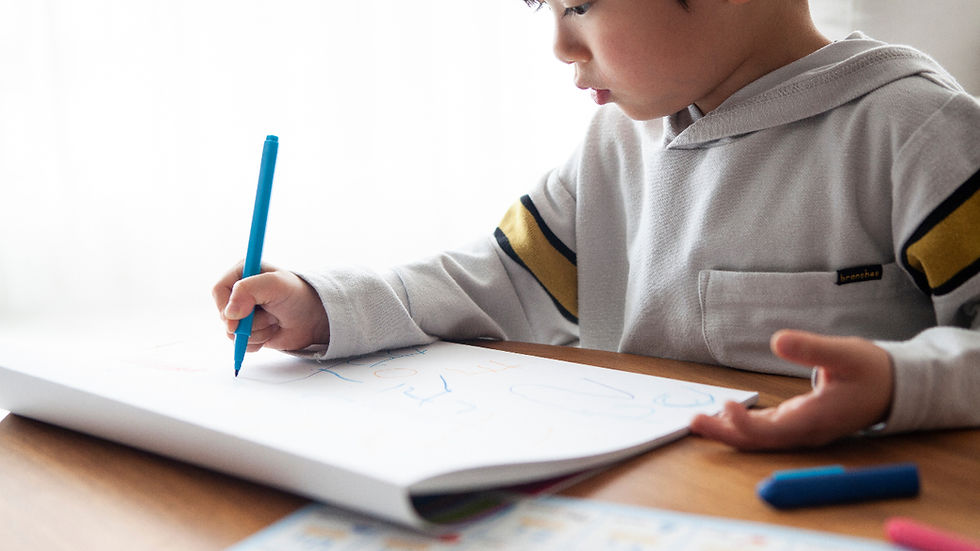



コメント